株価が割安か割高かを見る指標としてPER(株価収益率)があります。
一般的に、日本株ではPER15倍前後が一つの目安とされ、これより高ければ割高、低ければ割安と判断されることが多いと言われます。

では、日本を代表する小売企業イオン(8267)の現在のPERはどうでしょうか。
PERとイオン株の現状
結論から言うと、イオンのPERはこの15倍基準と比べて非常に高い水準にあります。
2025年夏時点でおよそ50倍前後で推移しており、これは同業のセブン&アイ・ホールディングス(約22倍)や小売業平均(20~30倍程度)と比べても明らかに高く、一般的基準の15倍と比べると桁違いに割高に見えます。
実際、過去にもイオン株はPER70~80倍以上と市場平均(15倍程度)に比べ極端に割高と指摘されてきました。
この記事では、イオンの現在のPER水準と過去数年間の推移を確認し、小売業界平均や競合他社のPERと比較します
その上で、個人投資家に人気の「株主優待」や高配当がある銘柄でなぜPERが高くなりやすいのか、その背景にある個人投資家の行動や人気株の傾向を解説します。
最後に、個人投資家がPER指標をどう使うべきか、特に優待株を評価する際の注意点について整理します。
1. イオンの現在のPER:15倍基準と比べて正常?
まず直近のイオンのPERを見てみましょう。
株価と利益水準にもよりますが、2025年8月時点でイオンのPERは概ね116倍程になっており、一般的な15倍前後という水準から見れば異常とも言える高さであることは間違いありません。
では、この水準は「正常」なのでしょうか?
結論としては、通常の基準からすればイオンのPERは割高であり正常範囲から逸脱しています。
一般にPER15倍程度が一つの目安とされる中で、たとえ50倍だとしてもその3倍以上、100倍なら6~7倍もの高さになります。
もちろん、PERは絶対的基準ではなく企業の成長期待なども織り込まれる指標です。
しかし、現状のイオン株価は利益に対してかなり高い評価がついていることは明白です。
この「高すぎるPER」について、投資家の間でも疑問に思う声は多く、「イオンの株価は割高ではないか?」という議論がよく見られます。
では、イオンのPERが過去にどのように推移してきたかを振り返り、この高いPERが一時的なものなのか常態化しているのかを確認します。
2. イオンの過去数年間のPER推移
イオンのPERは近年どのように変化してきたのでしょうか。以下に過去数年のイオンのPER推移(連結決算期末ベース)をまとめます。
- 2018年2月期:約61倍
- 2019年2月期:約83倍
- 2020年2月期:約63倍
- 2021年2月期:赤字決算(PER算出不可)
- 2022年2月期:約338倍
- 2023年2月期:約101倍
- 2024年2月期:約68倍
2021年に業績悪化で最終赤字となった際はPERが算出不能となりましたが、翌2022年には一時300倍超という極端な数値も記録しています。
その後業績回復に伴い2023年に約101倍、2024年に約68倍まで低下しましたが、それでもなお一般的基準から見れば状態的に高いPERです。
実際、過去5年間の平均PERは80倍以上にもなり「常に割高傾向」と分析する専門家もいます。
このように、イオンのPERが高いのは一時的な現象ではなく近年の恒常的な傾向であることがわかります。
言い換えれば、イオン株は慢性的に利益に対して株価が高めに評価されてきた銘柄と言えるでしょう。
次に、このイオンのPERを業界平均や他社と比較し、どの程度特異な水準なのかを確認します。
3. 小売業界・競合他社の平均PERとの比較
小売業界全体の平均PERはどれくらいでしょうか。
日本取引所グループのデータによれば、小売業の平均PERはおおよそ22.6倍程度とされています。

これは市場全体の平均と比べてもやや高めですが、小売業は利益率が低めな分PERが高く出やすい業種とも言われます。
では、イオン以外の具体的な企業を見てみましょう。
セブン&アイ・ホールディングス(3382)のPER
競合大手のセブン&アイ・ホールディングス(3382)では、2025年8月現在でPERは20~22倍程度と報じられています。実際、セブン&アイの直近PERは20倍前後(予想ベース)で推移しており、これは業界平均にほぼ沿った水準です。
ライフコーポレーション(8194)のPER
一方、食品スーパー中心のライフコーポレーション(8194)ではPER約12倍と、更に低い水準となっています。
ライフは堅実なスーパー事業が中心で成長率が緩やかな分、株価も収益に対して割安~適正水準に収まっていると考えられます。
これらと比較すると、イオンのPER(116倍超)は突出して高いことが明確です。
セブン&アイの約22倍や業界平均22倍と比べても5倍以上、ライフのような同業他社の12倍と比べれば9倍もの乖離があります。つまり、イオン株は同業と比べても格段に高いPERで取引されているのです。
この違いは何を意味するのでしょうか。
単純に考えれば、イオン株は利益に対して株価が割高に買われている(高評価されている)ことになります。
では、なぜイオンだけこれほど高い評価を受けているのか――その背景には将来の成長期待や事業構造上の特殊要因、そして個人投資家による人気などいくつかの理由が考えられます。
では次に、個人投資家に人気の優待や高配当という観点から、高PERの背景を探ってみましょう。
4. 優待・高配当銘柄のPERが高く評価されやすい理由
個人投資家に支えられる株価
イオン株のPERが高止まりする理由の一つに、個人投資家の根強い人気があります。
イオンは国内有数の株主数の多さ(約77万人)を誇り、その多くが個人株主です。
個人投資家にとってイオン株は「生活に身近で応援したい企業」であると同時に、魅力的な株主優待があるお気に入り銘柄です。
その結果、優待目当ての個人株主が長期保有することで株価が下支えされ、PERが高止まりする一因となっています
要するに、個人投資家による安定的な需要が株価を押し上げ、利益に比して高い株価(=高PER)を支えているのです。
イオンの強力な株主優待と“実質利回り”の高さ
イオン株の人気を支える最大の要因は、業界屈指とも言われる株主優待制度でしょう。
100株以上の株主に発行される「オーナーズカード」により、イオングループ各店での買い物金額に応じて3%~7%のキャッシュバックが受けられます。
キャッシュバックだけでなく、オーナーズカードを保有していれば、イオンシネマで映画鑑賞が1800円→1000円でいつでも800円OFFになる特定や、イオンオーナーズラウンジ(月8回まで)、専門店での割引など生活圏にイオンがある個人投資家にとっては使い思わず使い倒したくなってしまう内容でしょう。
※2025年9月の株式分割後は1%~からになります。
日常的にイオンで買い物をする家庭にとって、半年ごとに購入額の数%が返ってくるこの優待は非常に魅力的です。
例えば100株(現在約52万円強)を保有していれば、年間数十万円分の買い物に対して数万円規模のキャッシュバックが期待でき、配当(金銭)の利回り0.8%程度に加えて数%分の「実質利回り」を得られる計算になります。
この実質的な総合利回りの高さ・保有することの満足度が、多くの個人投資家を惹きつけています。
優待や配当によるメリットを重視する投資家は株価が多少割高でも手放さず、安定株主として居座る傾向があります
そのため、業績が多少低迷しても株価が下がりにくく、結果としてPERが高めに維持される傾向が生まれます。
イオン株が「割高」と言われながらも高値圏を保ち続ける背後には、優待を最大限活用する長期個人投資家の厚い支持があるのです。
高配当株も人気ゆえに売られにくい傾向
同様に、配当利回りが高い銘柄も個人投資家に人気です。
配当収入を目的に高配当株を長期保有する投資家が多いと、株価は下支えされやすくなります。
一般に、高配当=低PERであることが多いですが、もし業績一時悪化で利益が減少(PER上昇)しても、配当さえ維持されれば個人投資家が買い支えるケースもあります。
結果として株価が大きく崩れずPERが割高なままという状況が起こり得ます。
実際、「不況でも配当さえ出ていればホールド」という個人も多く、こうした心理が高配当銘柄の株価を支える要因となっています。
人気銘柄は「割高」でも買われる傾向
総じて、優待や高配当といった株主還元策が充実した銘柄は個人投資家からの人気が高く、需給面で株価が強含みやすい傾向があります。
人気株となった銘柄はブランド力や愛着も手伝って「欲しい人が多い状態」が続き、多少割高でも市場で買いが入りやすくなります。
同じような存在として他業種ではありますが、オリエンタルランドなどもこの典型例ではないでしょうか。

イオンや日本マクドナルド※のように常にPERが高めでも個人が買い支える銘柄が存在するのは、その典型的な例と言えるでしょう。
こうしたケースでは、市場平均的なPER基準だけでは測れない特殊要因(顧客・株主のロイヤリティ)が株価に織り込まれていると考えられます。
※参考: 日本マクドナルドHD(2702)はハンバーガー無料券などの優待が人気で、過去に大赤字決算を出した際も株価がほとんど下がらなかったほどです。優待狙いの個人投資家が下落局面で買い支えるためと見られています。反面、優待廃止の懸念が報じられた際には株価が急落する場面もありました。
5. 個人投資家のPER活用法と優待株評価の注意点
PERはあくまで目安の一つ
個人投資家にとってPERは、手軽に割高・割安感を測れる指標として広く使われています。
気になる銘柄の予想PERが15倍を下回っていれば「割安かな?」と感じ、逆に30倍を超えていれば「随分買われているな」と警戒するといった具合です。
実際、証券会社の銘柄ページなどでPERは簡単にチェックでき、初心者向け解説でも「PER15倍が一つの基準」とよく紹介されています。
しかし、PERだけに頼った判断には注意が必要です。
PERには業種ごとの標準値の違いや、一時的要因で利益がブレた場合の異常値など、押さえておくべきポイントがあります。
たとえば、小売業のように平均PER自体が20倍前後と他業種より高めの分野では、単純に15倍ラインで割安・割高を判断すると見誤る可能性があります。
このため、同業他社の水準と比較することが重要であり、市場全体の平均だけでなく業界平均や類似企業のPERを把握しておくと適切な判断につながります。
優待株のPERを見るときの注意点
特に株主優待が充実した銘柄を評価する際には、PERの見方に工夫が必要です。
優待人気の高い株は前述の通り業績より人気先行で株価が維持されやすく、PERが恒常的に高めになります。
このような銘柄では、「PERが高い=すぐ売り時」や「割高だから避ける」と単純に判断すると思わぬ機会損失や判断ミスにつながりかねません。実際、優待狙いの個人投資家に支えられた株は業績が多少悪化しても株価が下がりにくく、PERによる投資判断が難しいケースもあります。
一方で、優待株の高PERにはリスクも潜んでいることを忘れてはなりません。
人気に支えられている間は良いのですが、もし優待内容の改悪・廃止や業績の大幅悪化が起きた場合、今までのプレミアム評価が剥げ落ち急激に株価が調整する可能性があります。
前述の日本マクドナルドの例では、優待廃止の懸念報道で株価が急落し、多くの個人投資家に衝撃を与えました。
イオンについても、たとえば優待キャッシュバック率の変更や配当の減配などがあれば、高いPERを正当化していた要素が揺らぎ株価が調整するリスクがあります。
PERと合わせて見るべき指標やポイント
個人投資家が優待株を評価する際には、PER以外の指標や定性的なポイントも確認しましょう。
例えば、PBR(株価純資産倍率)やROEなどで財務健全性や資産価値を把握する、配当性向を見て配当維持の余力を判断する、といったことが有効です。
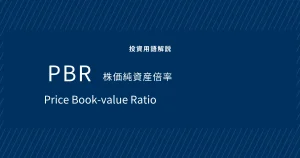

また、「優待込みで実質利回り何%くらいになるか」を試算し、そのメリットと株価水準を天秤にかけてみるのも一つです。優待や配当でどれだけリターンが得られるかが明確になると、現在のPERの高さが許容範囲かどうか判断しやすくなります。
さらに、企業の将来性や利益成長見通しにも目を配りましょう。
高PERが許容される背景には「今は利益が小さいが将来大きく伸びる」という期待が織り込まれている場合もあります。
もし優待株であっても将来の利益成長が期待できるなら、高いPERも成長によって是正されていく可能性があります。逆に、成長が見込めず優待以外に魅力がない場合、高PERのまま停滞し続けるか、人気が薄れれば株価が下落するリスクもあります。
まとめ
イオンの現在のPERは一般的基準の15倍から見れば明らかに異常値とも言える高さですが、それにはそれなりの理由と背景があります。
DX戦略や不動産資産価値、金融事業とのシナジー、海外展開といった将来への期待、そして何より最強クラスの株主優待による個人投資家の厚い支持が、「一見高すぎるPER」をある程度正当化している面があるのです。
株価は足元の利益だけではなく市場の期待を映す鏡でもあり、イオンの場合その期待値が同業他社より高く織り込まれていると言えるでしょう。
個人投資家としてイオン株を見る場合、優待や配当を含めた総合的なリターンを考慮しつつ、それでも割高すぎないか慎重に見極める姿勢が大切です。
PERは便利な指標ですが万能ではありません。
特に優待株では「人気」という見えざる価値がPERを押し上げることを念頭に置き、数字の裏側にある要因を読み解く必要があります。
イオンのような人気優待銘柄に投資する際は、優待の魅力と株価水準のバランス、そして企業の本質的な収益力を冷静に評価していきましょう。
それが、長期的に後悔しない投資判断につながるポイントです。






コメント